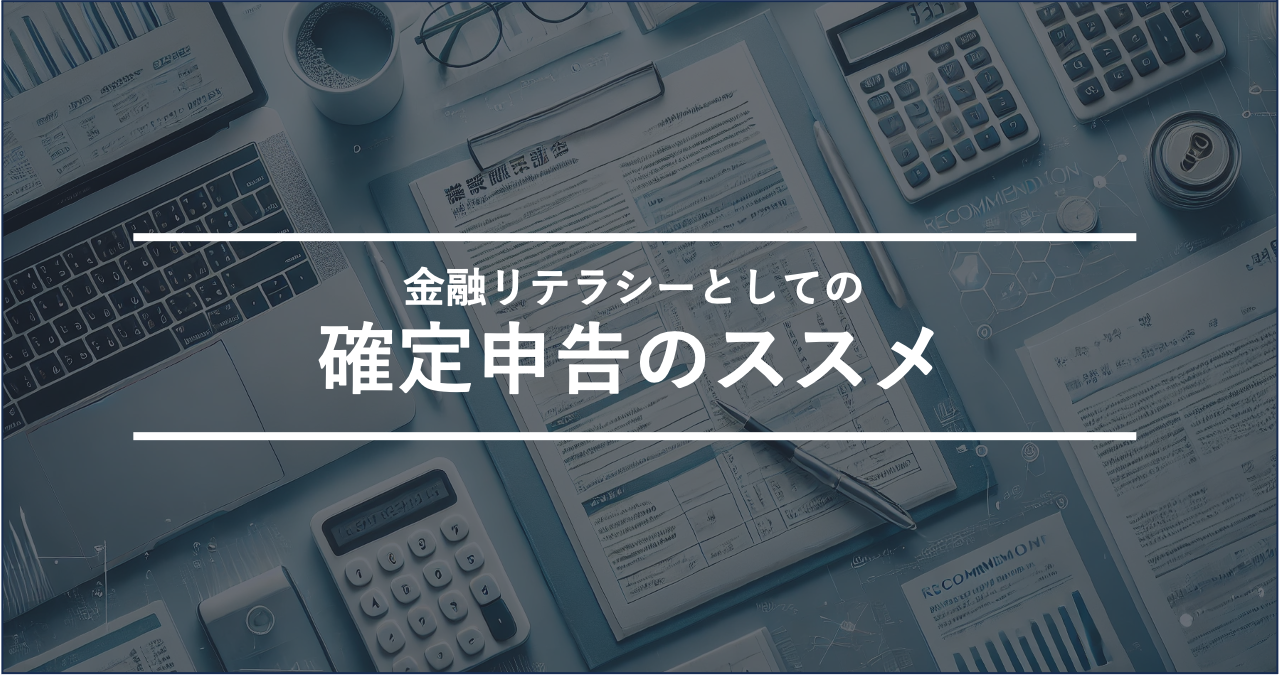今年も確定申告の時期がやってきました。
私はふるさと納税の寄附先が6件以上なことと、繰越控除を使いたいので毎年確定申告を行っています。
確定申告をしていると、不思議と税制やお金の知識が身につくので、あまり還付に期待ができない会社員の場合でも確定申告をするのは意味があると考えています。
はじめに:確定申告は一部の人のものではない
「確定申告」と聞くと、フリーランスや個人事業主が行うものというイメージを持つ人が多いかもしれません。
しかし、会社員でも医療費控除やふるさと納税、副業収入の申告が必要になるケースがあり、決して一部の人だけの話ではありません。
さらに、これからの時代は「給与収入だけではなく、複数の収入源を持つ」収入の多様化が一般的になっていきます。
副業や投資、不動産収入など、会社員であっても確定申告が必要になる場面は増えていくでしょう。
確定申告を理解することは、単に税金対策を学ぶだけではなく、「お金の流れを知り、賢く管理する力」を身につけることにつながります。
そして、この知識を持つことが、親としての金融リテラシー向上にも直結し、子どもへのお金の教育にも役立ちます。
なぜ親世代にとって確定申告の知識が必要なのか?
収入の多様化と税金の関係
近年、副業解禁の流れやフリーランス人口の増加により、収入の形が多様化しています。これまで「会社員だから確定申告は関係ない」と考えていた人も、以下のようなケースでは確定申告が必要になります。
- 副業で年間20万円以上の収入がある場合
- 医療費控除やふるさと納税の控除を受けたい場合
- 投資の利益(株式売却益や配当)が出た場合
確定申告を知らないと損をする
確定申告をしないと、払い過ぎた税金を取り戻すチャンスを逃してしまいます。
例えば、
- 医療費控除を活用すれば、大きな医療費を支払った年の税負担を軽減できる
- ふるさと納税の仕組みを理解すれば、実質2,000円で自治体の特産品を得られる
その他にも様々な控除が存在します。
e-Taxではオンラインで全ての確定申告が済みますが、入力を進めていると様々な控除が存在することを知ります。
普段は自分に関係のある所得控除くらいしか意識しませんが、「こういう控除もあるのか」という知識が勝手にたまっていきます。
その知識があると、今後の人生において「これは所得控除の対象だな」とか、毎年の税制の変化にも耳を傾けることができるようになります。
これらは確定申告をやっているかどうかで(実益としても)差が出る部分です。
子どもへのお金の教育のためにも
親が税金やお金の流れを理解していれば、子どもにも自然と「お金の仕組み」を伝えやすくなります。
「税金って何?」という問いに答えられる親になることが、子どもの金融リテラシー向上につながります。
また、収入の多様化は恐らく子どもたちの時代により顕著になるでしょう。
単純な職業や収入の是非のみでなく、税制を含む様々な知識を親が持っていることは子どもにとって大きな後ろ盾になり得ます。
確定申告を通じて親が身につけるべき「お金のリテラシー」
確定申告が必要なケースと手順を理解する
どういった場合に確定申告が必要、あるいはやった方がお得か、を知り、各ケースごとの手順を理解します。
- 給与所得のみ
- 複数の給与所得がある場合
- 副業といった事業所得がある場合
- 不動産所得や他所得がある場合
- 還付の場合
- 納税の場合
など、一概に確定申告と言ってもどういったケースでどういった申告が必要か異なります。
税金の基礎を理解する
- 所得税の仕組み(累進課税)
- 会社員とフリーランスの税制の違い
- 確定申告で受けられる主な控除(医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税 など)
会社員の場合、給与明細で何が引かれているかを見ますが、所得税の税率や社会保険の決定額がどのように決まっているかまでを気にすることはあまりないと思います。
なかなか税制について勉強をする機会もないので、強制的に年に1回勉強できる機会を作ってしまうのは良い手段だと思います。
経費の概念を学ぶ
副業やフリーランスでは、収入から経費を差し引いた分が課税対象となります。
例えば、自宅の一部を仕事用に使っている場合、一部の家賃や通信費を経費に計上できるケースもあります。
一般的に経費=会社のお金で好きに使える、といったイメージがありますが、実体はどういったものかを知ることは、今後の自身のためにもなると思います。
投資と税金の関係を知る
- 株や投資信託の売却益には約20%の税金がかかる
- NISAやiDeCoを活用すると非課税メリットがある
- 不動産投資などでも確定申告が必要になるケースがある
NISAのみの場合や、特定口座で源泉徴収を受けている場合は確定申告が不要ですが、外国株の売買での利益や、外国株の配当収入がある場合に多少の税控除を受けられます。
これは確定申告をしないと戻ってこない税金です。
親が確定申告を学ぶことで得られる3つのメリット
ムダな税金を減らせる
- 会社員でも、ふるさと納税や医療費控除で税金を取り戻せる
- 知らないと受けられない控除が多い
家計管理や投資の知識が深まる
- 「収入・支出・税金」の関係を理解できる
- 家計の見直しや資産運用にも役立つ
子どもへのお金の教育につながる
- 税制について説明できる
- 家計管理の視点を子どもにも伝えやすくなる
まずはここから 親が学ぶべき確定申告の基礎
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を触ってみる
「作成開始」からe-taxで申告書類の作成ができます。提出さえしなければ良いのでまずは触ってみることをオススメします。
ただ、最終的に提出するのとしないのとでは身の入り方が変わると思いますので、
「確定申告をやらないと損」という状況を作ってみるのも有りだと思います。
例えば「ふるさと納税の寄附先を6以上にする」「上場株式の売買で損が出た場合に繰越控除する」など。
※ふるさと納税のワンストップ特例は5つの自治体まで。6以上は確定申告が必要。
※損失の繰越控除は最大3年間。損が出た翌年に利益が出れば、前年分のマイナス分で控除できる。ただし、1回繰越控除したら3年間は毎年確定申告が必要。
簡単な確定申告シミュレーションをしてみる
- 「もし副業を始めたら?」を想定し、税額を計算してみる
たとえば副業で年間に100万円の売上(事業収入)を得た場合、などの仮をイメージして申告書の作成をしてみるのも有りかもしれません。
すぐに活用できる制度を試す
- ふるさと納税を試してみる
- 医療費控除の活用
- 住宅ローン控除の活用
- iDeco(小規模企業共済等掛金控除)
これらは年末調整で済んでしまいますが、年末調整をした方でも確定申告はできます。年末調整をしなかった場合をイメージして作成してみるのもいいと思います。
まとめ:確定申告を学ぶことが、未来のお金の安心につながる
確定申告は、税金の仕組みを理解するための最適な機会です。
私がこれまで学んだこととしては、
- 損失の繰越控除は株式と先物取引(FXやCFDなど)で合算できない
- 株式や先物取引の利益の繰越はできない
- 暗号資産(仮想通貨)は雑所得扱いになるが、利益の額によっては株式の課税より安い
- 扶養の知識
- 生命保険の控除の渋さ(上限があり、あまり税メリットがない)
- iDecoの控除の優秀さ(まるまる課税控除の対象)
- 運用益より課税控除で戻るお金の方が大きいケースもある(私はそう)
「税金を知ることは、お金を守ること」です。
親自身が学び、活用することで、お金のリテラシーを向上させ、子どもにも良い影響を与えることができます。
まずは「知ること」から始め、実際に試してみることで、お金の知識を深めていきましょう。