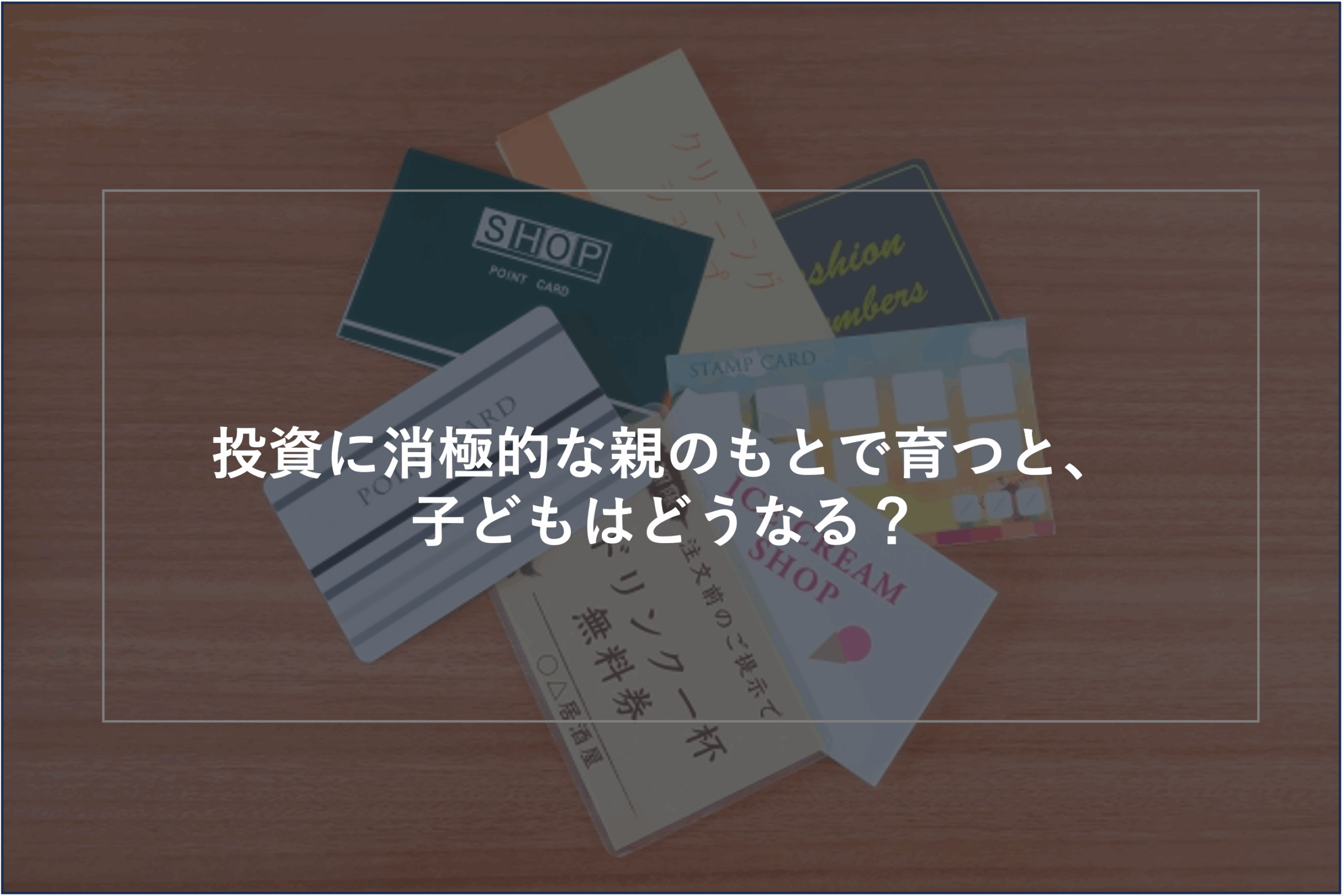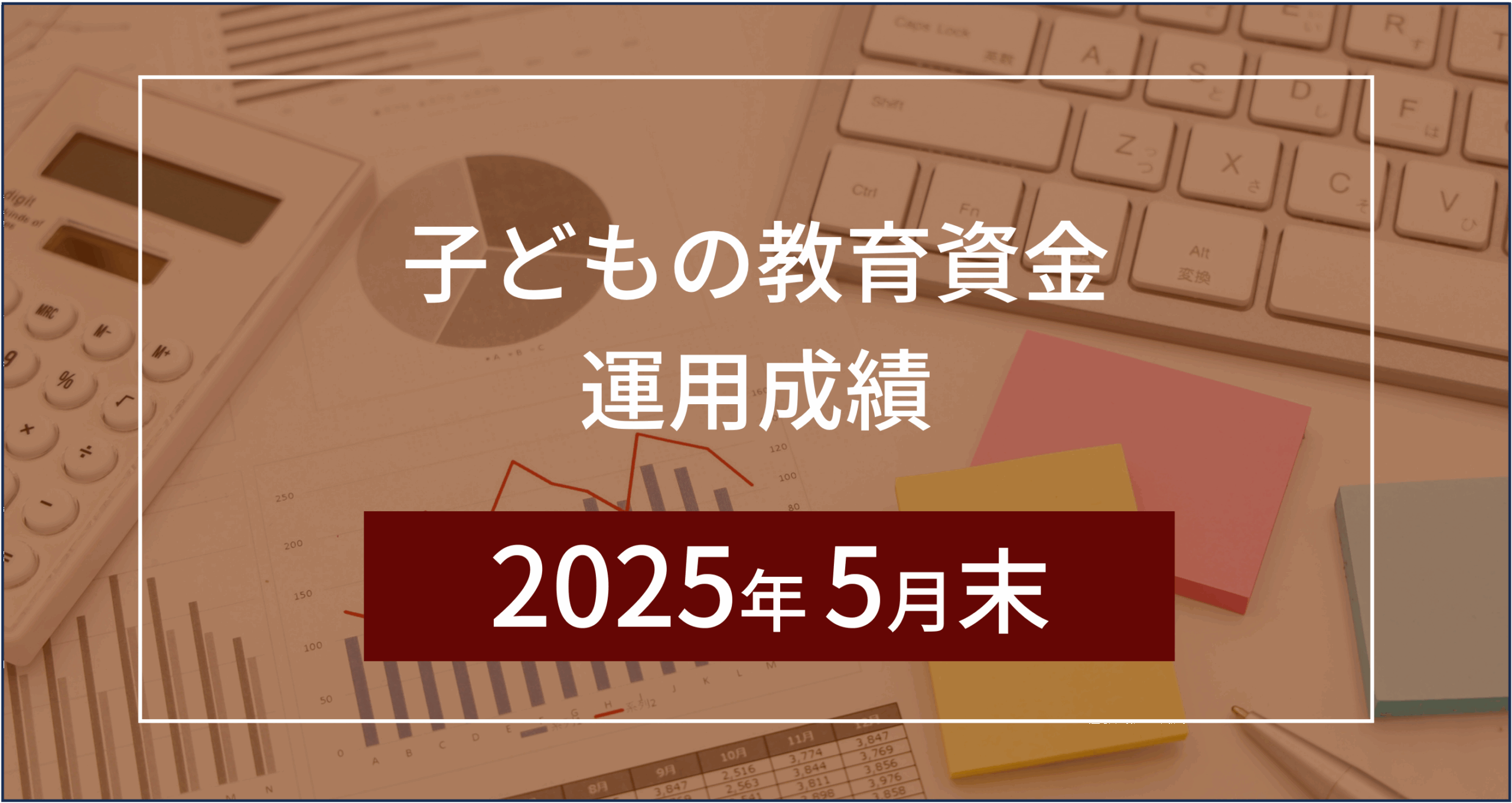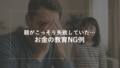最近は、NISAの拡充などもあり、投資に関心を持つ人が増えてきました。
金融庁の発表によれば、2024年末時点で新NISAの口座数は1,000万を超えたそうです。
“貯金一択”が当たり前だった時代に比べれば、大きな変化です。
ただ、投資への関心が高まっているとはいえ、それを家庭の中で、日常的に話しているか?と問われると、「まだそこまでではない」という人も多いのではないでしょうか。
実際、私自身も意識はしつつも、投資の話を全面的にするのはいまだに億劫です。
そういえば、自分の親も株や投資信託の話なんて一度もしてなかったな……なんて思い出します。
子どもは親のお金感覚をそのまま受け取る
家庭の中では、お金の話題はタブーになりがちです。
「おこづかいはいくら?」「どう使ってる?」とは聞くけど、「どうやってお金を増やすか」は(少なくとも私の記憶では)全く話題に出ませんでした。
でも実は、投資に対する親の姿勢が、そのまま子どもに伝わることって少なくないのだと思います。
たとえば「うちは投資とかはやらないから」「損しそうで怖いよね」といった何気ない一言。
それが積み重なると、子どもにとって投資は“危険で避けるべきもの”になってしまいます。
投資を知らないまま育つと、どんな影響がある?
私自身がそうだったように、投資に無縁のまま大人になると、以下のような影響が出る可能性があります。
- 「お金は稼いで使うか、貯めるか」の二択しか持たなくなる
- 時間を味方につける“複利”や“資産形成”の概念が育たない
- 将来、資産運用や年金準備で出遅れてしまう
- そもそも投資の仕組みやルールがわからず、情報に振り回されやすくなる
もちろん、投資がすべてではありません。
でも、“選択肢として持っていない”こと自体が、大きな不利になってしまうこともあるのです。
投資が身近な家庭で育った子どもは?
一方で、親が投資に前向きな家庭では、「投資=特別なこと」ではなくなります。(欧米はこの意識になっているように感じます)
たとえば食事中に「株主優待でこのハンバーガーもらえたよ」なんて会話があれば、
子どもは自然と「株って面白そう(またはおトク)」「応援する会社を選べるんだ」と思えるようになります。
投資を通じて社会や経済に目を向けたり、失敗してもそれを「学び」に変える経験ができる。
それって、学校ではなかなか教えてくれない“生きたお金の教育”だと思うのです。
子どもと一緒に楽しめる“投資体験”とは?
家庭内で投資の話をどう扱うか、どうやって子どもに伝えるかは難しいところだと思います。
でも最初から難しい話をする必要はありません。
投資に関心があるなら、まずは「親がやってみる」だけでも、立派な一歩です。
そのうえで、子どもと一緒に株主優待がある企業を探してみるのもおすすめです。
「マクドナルドの無料券がもらえる株があるんだよ」
「この回転寿司チェーン、優待で食事券が届くんだって」
そんな話題からでも、子どもは投資に対してポジティブな印象を持ちやすくなります。
たとえば…
- 日本マクドナルドHD(2702):無料食事券
- サンリオ(8136):テーマパーク優待券
- タカラトミー(7867):「トミカ」「リカちゃん」
- すかいらーくHD(3197):ガスト・バーミヤンなどで使える食事券
- サーティワン アイスクリーム(2268):電子ギフト券
- イオンファンタジー(4343):モーリーファンタジーで利用可能な優待券
我が家では、クリエイト・レストランツHD(3387)を保有してます。おしゃれなレストランが多いので、子どもたちの誕生日やなにかの記念日に優待券で食事してます。
こんなふうに、「子どもが知っている企業」で、「実際に恩恵を受けられる」優待を選ぶのは、
投資を“楽しいもの”として理解してもらうのにぴったりだと思います。
投資は“儲けるため”だけじゃない
「投資」というと、“お金を増やす手段”として語られがちです。
でも、最近思うのは、
子どもと一緒に未来を考えたり、自分のお金をどう使うかに向き合うきっかけとして、
投資ってとっても有効なのではないかと。
お金を「ただ使うもの」「ただ貯めるもの」ではなく、
「育てるもの」として伝えていけたら、きっと子どもにとっても大きな財産になる。
そんなふうに思っています。