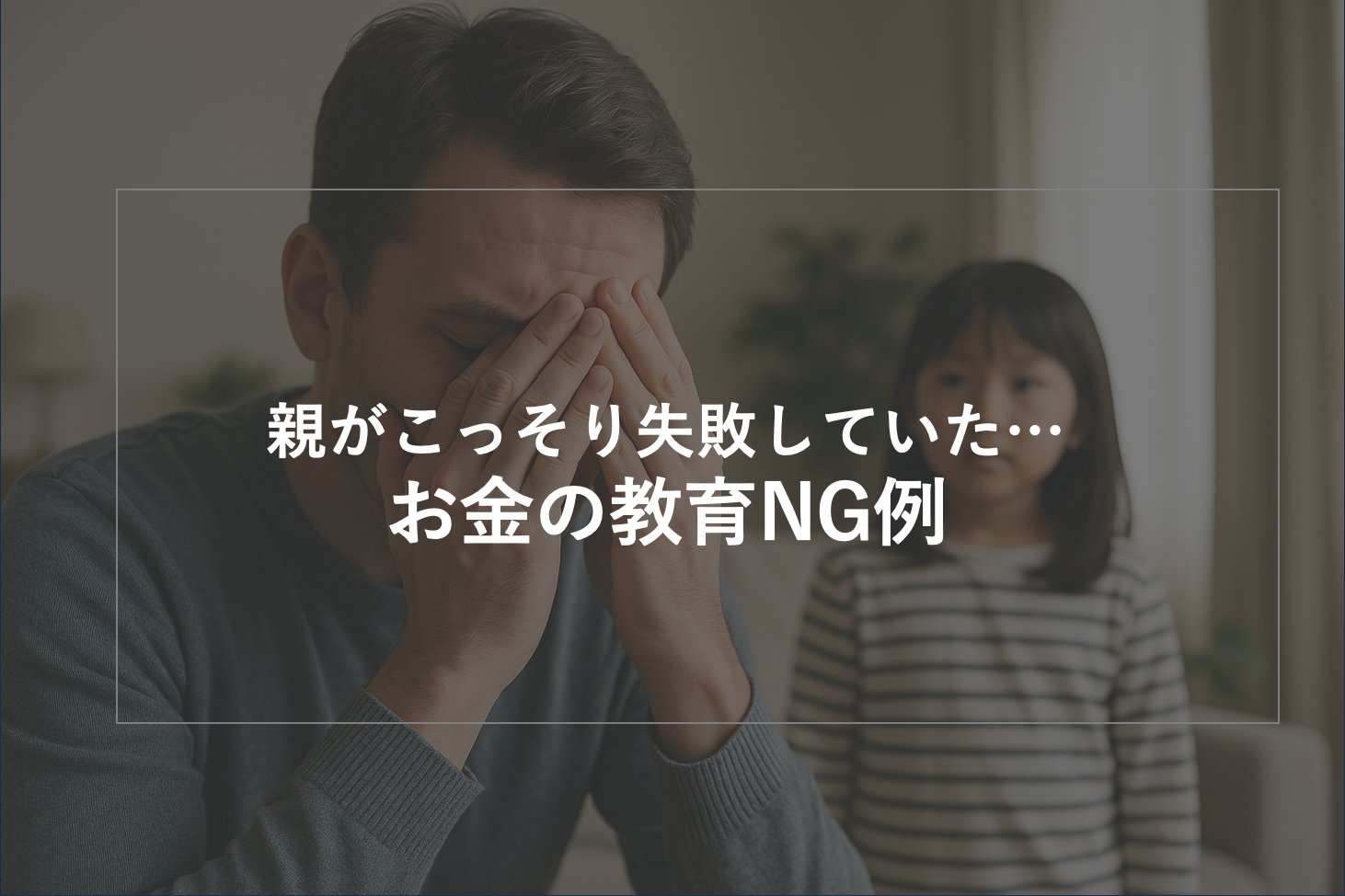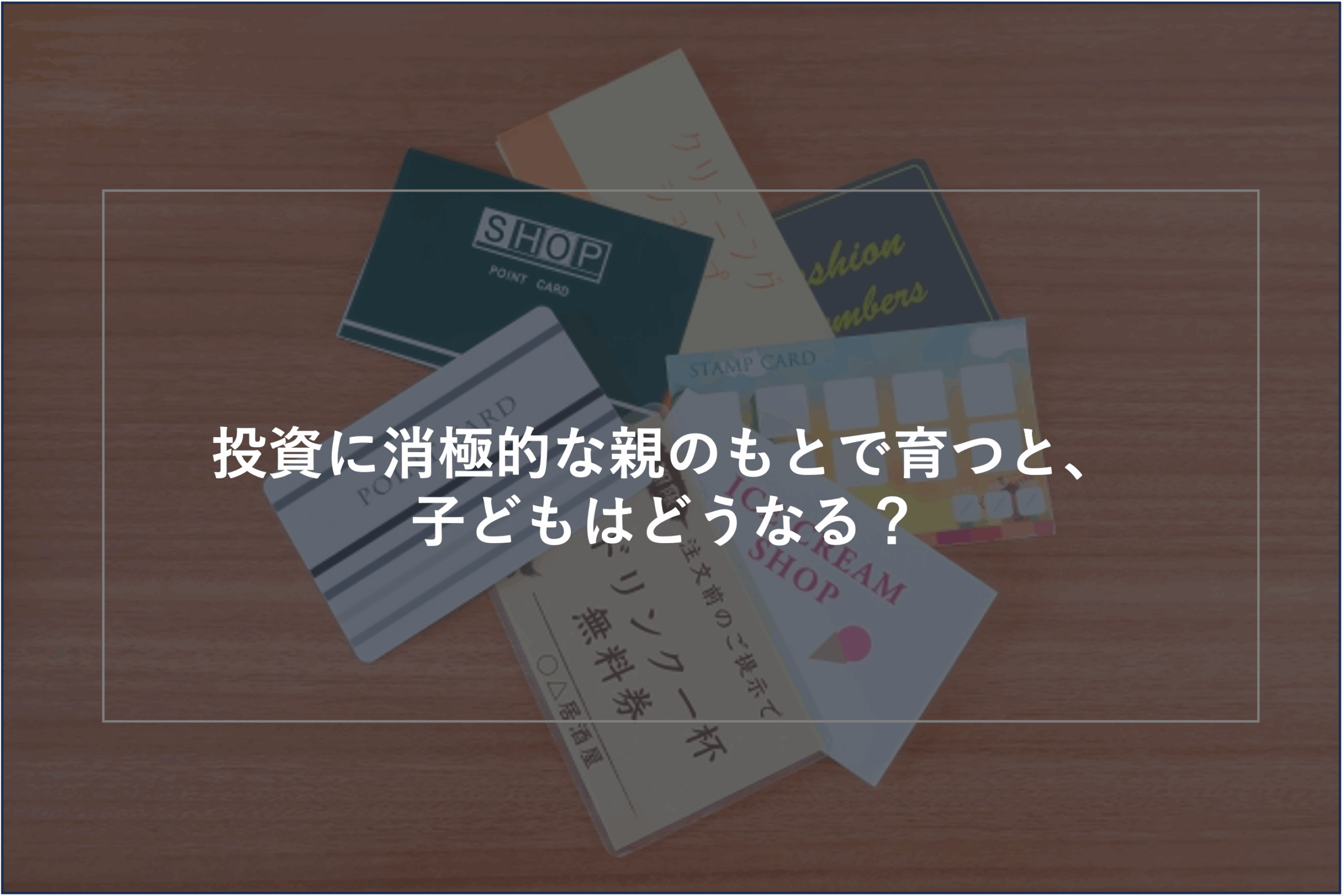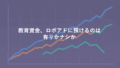このブログではたびたびお金の教育における親の姿や親の経験の影響の大きさを記事にしてきました。
「お金の教育」と聞くと、正しく教えなければいけない、きちんと知識を身につけさせなきゃと力が入ってしまうもの。でも実際には、「知らず知らずのうちにやってしまっているNG行動」のほうが、子どもにとっては強く印象に残ってしまうことがあります。
今回は、親がついやってしまいがちな“お金の教育の落とし穴”をご紹介します。自戒を込めつつ、、一緒に見直していきましょう。
「うちはお金がない」が口ぐせになっている
買い物中、子どもが「これ欲しい!」とせがんだとき、「そんなの買えるわけないでしょ」「うちはお金ないから」と反射的に言ってしまったことはありませんか?
本当にお金が足りないわけではなくても、「無駄遣いしたくない」「教育的に買い与えたくない」という親の判断で使うことが多いこの言葉。でも繰り返すうちに、子どもの中では「お金=常に足りないもの」「自分の欲求は抑えるべきもの」といった、偏った認識が育ってしまうことがあります。
伝えるなら、「今は買わないと決めてる」「これは買う価値があるか一緒に考えよう」など、理由と判断をセットにする言い方がおすすめです。
抑えつけるのではなく、理由を話して納得してもらうことが大切です。なかなか子どもには伝わらないのですが、諦めることは子どもにとっても親自身にとっても良くないことです。
お金の話を家庭内タブーにしている
「お金のことは子どもが気にしなくていい」——これも、親の優しさから出る言葉です。
でも、これが繰り返されると、子どもにとっては「お金の話はしてはいけないもの」「大人だけのもの」と思わせてしまう可能性もあります。
お金は生活の一部であり、社会の仕組みと深く関わっています。日常の中で、「どうしてこの商品を選んだのか」「どれくらい働くとこの金額になるのか」など、簡単な話題から少しずつ共有していくことが、自然なお金の教育になります。
私は日本の家庭において、お金の話=タブーというのが根本的によろしくないと常々考えています。かといっていきなり全てをオープンにしていくことも難しいと思います。
徐々に浸透させていたきたいですし、自分の子どもが親になったときにも意識してもらいたいと思っています。
ごほうびで「お金」を乱用する
「テストで100点取ったら100円あげる」「お手伝いしたら50円」など、努力に対して報酬としてお金を与える方法は、動機づけとして一定の効果があります。
ただ、それが続くと「何かしないとお金はもらえない」「逆に言えば、やれば必ずお金がもらえる」という条件反射のような思考になるリスクもあります。
また、努力(や労働)対価として一定の報酬を得続けること自体が限界効用逓減に繋がるため、どこかで報酬の引き上げが必要になってしまいます。
それ自体が悪いことだとは思いませんが、ごほうびを使うなら、「ありがとう!助かったよ」「この仕事にはこんな価値があるんだね」といった言葉のフィードバックとセットで、お金以外の価値も伝えていきたいところです。あくまでお礼のカタチを取り、お金自体を目的としない思考も養っていきたいです。
「見せたくない支出」を隠している
例えば、ネットショッピングで自分のものを買ったときに「これはポイント使ったからタダみたいなもん」などと軽くごまかす場面。つい言ってしまいがちですが、子どもはそんなことにはすぐ気づきます。これが続くと「お金の出入りはごまかせるもの」「本当のことは言わなくてもいい」といった印象を与えてしまいます。
子どもに見せる場面こそ、正直に伝えるチャンスです。「これはちょっとしたごほうびで買ったんだ」「節約してた分で買ったんだ」など、判断のプロセスを見せていくことが子どもの納得感や信頼にもつながります。
親自身が“買い物依存”を自覚していない
ストレスがたまったときに「ちょっとくらい買ってもいいよね」と頻繁に買い物をしてしまう。買ったもので部屋があふれている。そんな行動、子どもは意外とよく見ています。
「必要なものを考えて買う」「無駄遣いしないように選ぶ」など、言葉では正しいことを教えていても、日常の行動が矛盾していれば、子どもには「親は言ってることとやってることが違う」と映ってしまいます。
まずは自分の消費行動を客観的に見つめ直すところから始めてみましょう。
「投資は怖いもの」と決めつけている
少し子どもが大きくなってきたとき、テレビやニュース等で投資の話題が出るときがあると思います。
そういったときに「株とかやめときなさい」「投資は危ない」など、過去の失敗やニュースの印象から、投資=ギャンブルのように考えている人も少なくありません。(祖父母などから言われることも)
しかし現代の日本でも、長期・分散・積立など、リスクを抑えた形で資産形成を行う考え方が一般的になりつつあります。おおよそ怖がっているのは知らないから、が多いです。
子どもには、「リスクがあるからこそ知っておいたほうがいい」「学べば怖くないものもある」という視点を伝えていけると、より広いお金の世界を見せることができると思います。
まとめ
お金の教育は、「教えるぞ!」と構えるよりも、日常の中にある言葉や行動から伝わっていくもの。だからこそ、「無意識のうちにやっているNG行動」こそ見直す価値があります。
完璧な親である必要はありません。でも、「自分も見直してみよう」と思うその一歩が、子どもにとっては何よりの学びになるかもしれませんし、子どもと一緒に学んでいこう、という姿勢こそ子どもにとっても納得感のあるカタチかもしれません。