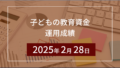何事もそうですが、子どもは親の生き方をトレースし、それを望もうが望むまいが親と同じ行動や価値観を持つケースが非常に多いと感じます。
遺伝の影響も大きいと思いますが、金銭感覚については家庭環境の要因が大きいと思います。
親の金銭感覚は子どもにどう影響するか
子どもは親の行動を無意識に模倣しますが、特に金銭感覚は、親の価値観や生活習慣が強く影響する部分です。以下のような親の行動が、子どもの金銭感覚に影響を与えます。
- 浪費型の親 →「お金があればすぐ使う」が当たり前
- 倹約型の親 → 必要以上に節約志向になり、お金を使うことを怖がる
- 計画的な親 → 子どもも「お金の管理」を自然と学びやすい
- 無関心な親 → お金の扱い方を学ぶ機会を失う
子どもは「お金の使い方」だけでなく、「お金との向き合い方」も親の影響を受けるため、親自身がどのようにお金と付き合っているか、また自身の親がどういった金銭感覚か(だったか)を振り返ることが大切です。
間違った金銭教育の例
子どもの金銭感覚を歪める可能性がある親の行動をいくつか紹介します。
- 「お金がない」が口癖になっている
→「お金がない=不安」と刷り込まれ、お金に対してネガティブな印象を持つ - 必要なものでも我慢させすぎる or 何でも買い与える
→ 極端な節約や浪費は、バランスの取れたお金の使い方を学ぶ機会を奪う - お金の話をタブー視する
→ 家庭でお金の話が出ないと、子どもは「お金の話をしてはいけない」と思い、正しい知識を得る機会を失う - キャッシュレス決済ばかりで現金の流れを見せない
→ お金が「見えない」ことで、使いすぎやお金の価値を理解しにくくなる
現金が子どもにとってお金のことを学ぶ良い機会ではありますが、キャッシュレス決済は実益があるためなかなか難しいところではあります。
正しいと思う金銭教育のコツ
そもそも親自身が「正しいと思う金銭感覚がなにか」が定義されている必要があります。
例えば、計画的に収入や支出を管理し、ライフイベントに合わせた資金繰りが出来ていること、なのか。
収入のなかであれば好きに使っても良いと考えるのか。
個人差もあり、且つケースバイケースによる、というところが大きいです。
少なくとも、「こうあって欲しい」と思う金銭感覚があるのであれば、親自身がそれを身につけている前提は必要です。
では、どのようにすれば子どもに健全な金銭感覚を身につけさせられるのでしょうか?
1.おこづかいを通じて「管理する力」を育てる
→ おこづかい帳をつけさせる/収入・支出を可視化する
2.お金の使い道を一緒に考える習慣をつける
→ 「本当に必要?」「ほかに選択肢は?」と問いかける
3.家計の話をオープンにする
→ 例えば「旅行の予算は〇万円で、交通費に〇万円かかる」など具体的に話す
4.キャッシュレス時代でも現金の流れを理解させる
→ ATMでお金を引き出す場面を見せる/クレジットカードの仕組みを説明する
5.親自身が「お金の知識」を学び続ける
→ 親が投資や資産運用について学ぶと、子どもも自然と興味を持つ
特に、「家計の話をオープンにする」というのを私は重要視しています。
これは自身の経験から来るものですが、幼少期に家で親がお金の話をしているのを聞いたことがありませんでした。
自分が進学したときの学費、一人暮らしの生活費、様々なものをただ与えられて過ごしており、いい意味でも悪い意味でもお金に対して関心が薄かったです。
中学生くらいになると、金額の価値や労働収入の相場もある程度知るようになります。
家計をベースに、親が計画的に考えていることを子どもに見せることこそ、正しい金銭感覚を身につけさせる良い方法でしょう。
まだまだ子どもたちが小さいので、あんまり伝わっていないかもしれませんが、意識的に妻とはお金の話をオープンにするよう心がけています。
親の金銭感覚は、子どもに大きな影響を与えます。まずは親自身が「お金に対してどう向き合っているか」を振り返り、日々の生活の中で子どもに正しい金銭感覚を伝えることが大切です。
お金の話をポジティブにし、楽しみながら学ぶ環境を作ることで、子どもは自然と「お金を管理する力」を身につけることができるでしょう。