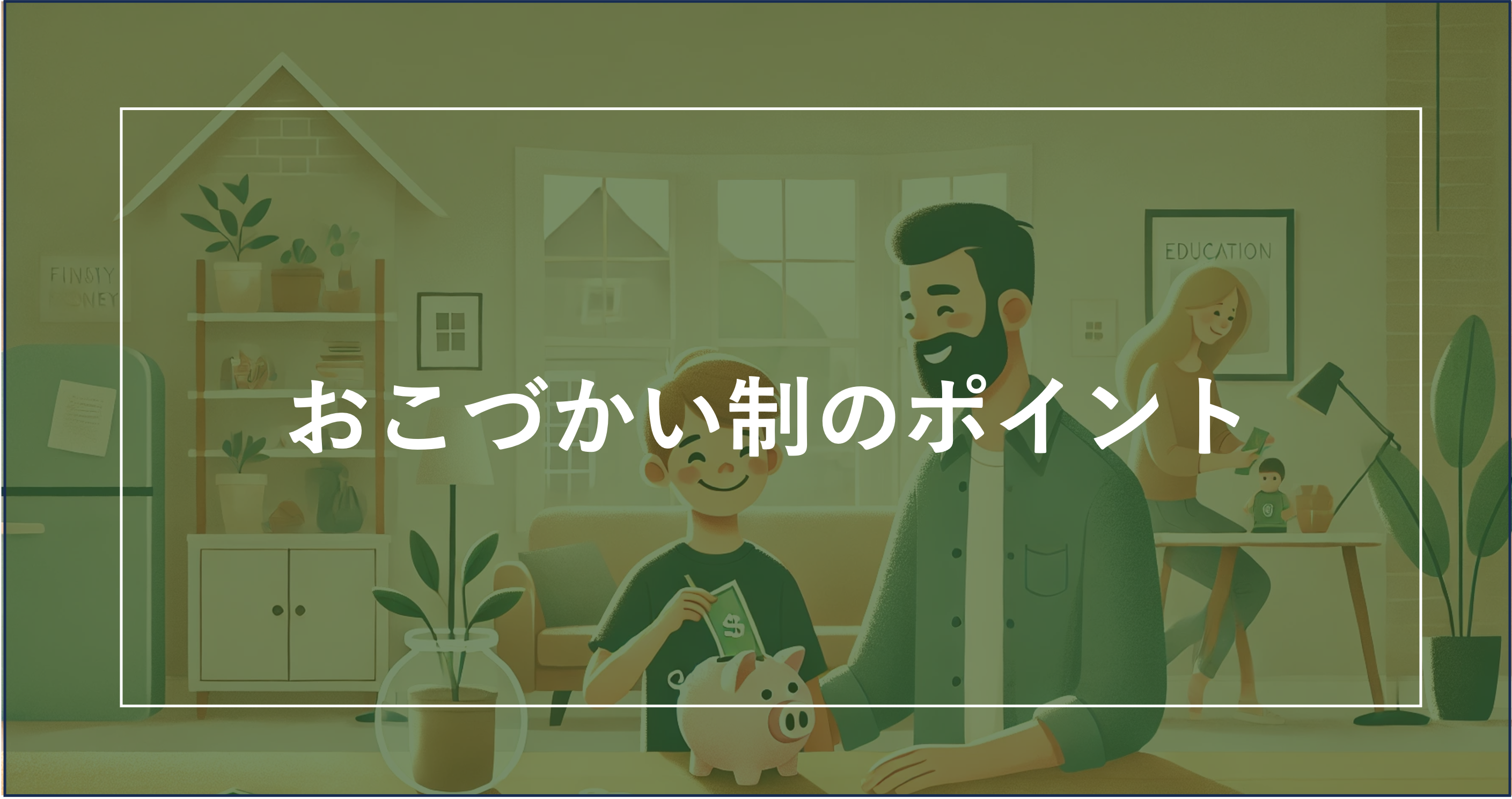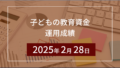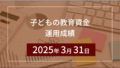「そろそろ、おこづかいってあげたほうがいいのかな?」
子どもが小学生になり、買い物やお金に興味を持ち始めると、多くの親が一度は考えるテーマです。
特に7歳くらいになると、数字への理解が深まり、生活の中で「お金を使う」場面が少しずつ出てきます。
今回は、7歳前後(小学1年生)の子どもに向けたおこづかい制の始め方について、実践的なポイントや考え方を紹介します。
おこづかいは、ただのお金ではなく「お金を使いこなす力」を育てる第一歩。家庭でできる金融教育として、今注目されています。
なぜ今「おこづかい」が大切なのか?
金融教育というと、「投資」や「税金」のような難しいイメージがあるかもしれません。でも、お金の価値や管理のしかた、使い方の善し悪しといった基本的な感覚は、もっとずっと早い段階から育てることができます。
学校でも2022年から「金融教育」が高校の家庭科に加わるなど、社会的にも注目が集まっていますが、小学生のうちに「お金に対する素地」をつくることこそ、長い目で見て大切な教育なのです。
おこづかいは、そうした学びの入り口として最適な手段のひとつです。子どもにとっては自由に使える「自分のお金」を持つことで、お金の大切さや管理の仕方を実感できます。
いつから始める?「おこづかいデビュー」のベストタイミング
おこづかいを始める時期に「絶対」はありませんが、多くの家庭では小学校1〜2年生の7〜8歳ごろから始めているようです。この時期は、簡単な計算や数字の理解ができるようになり、コンビニやスーパーでの買い物など、お金のやり取りに興味を持ち始める頃。
こんなサインが出てきたら、始めどきかもしれません。
- お店で「これ買いたい」と言うことが増えた
- 自分でお金を払ってみたがる
- おつりや値段に興味を持ち始めた
子どもが「自分で決めたい」「自分で買いたい」という気持ちを持ち始めたときこそ、おこづかい制のスタートにぴったりです。
どう始める?おこづかい制のポイント3つ
いざ始めようと思っても、気になるのは「いくら渡す?」「いつ渡す?」「何に使わせる?」といったルールづくり。ここでは、家庭で無理なく続けるための基本のポイントを3つ紹介します。
1. 金額は“年齢×100円”がひとつの目安
7歳なら700円、8歳なら800円など、子どもの年齢に応じた金額設定が一つの定番。もちろん、家庭の状況や地域の物価によって調整してOKです。
また、周りのお友達におこづかい制の子がいれば金額を参考に合わせるのも一つです。
2. 渡す頻度は「月1回」がスタンダード
毎週よりも月1回の方が管理しやすく、長期的な見通しも立てやすい傾向があります。1ヶ月でどう使うかを考える力も養われます。
3. ルールは“ゆるすぎず、厳しすぎず”
「おやつには使ってもいいけど、ガチャガチャはダメ」など、家庭ごとにルールを決めると安心ですが、あまりに制限が多いと逆効果に。基本は「自分で考えて使わせて、失敗から学ばせる」くらいの距離感が理想です。
4. 時折会話ベースのアドバイスをする
たまには親からもこうしたら?といったアドバイスをしてあげるべきです。しかし出来るだけ子どもからの報告や相談があったうえでのアドバイスとなるのが理想的です。
お金のことについて興味を持ってもらえるように導いてあげましょう。
「使いすぎた!」なども大事な学び
実はおこづかい制における最も重要なことは、失敗経験です。
後から振り返って無駄遣いと気付ける子はそう多くないと思います。失敗を失敗と思うことすら難しいかもしれません。
ですが、「欲しいものを全部は買えない」「いらないものを買ってしまった」「使いすぎて早くに無くなった」など、少しづつお金での失敗を積んで欲しいのです。
もちろん、ただ失敗するだけではなくそこからの学びが重要になります。
「どうして足りなかったんだろう?」「来月はどうすればいいかな?」と親子で話し合うことで、お金に対する感覚が自然と身についていきます。
完璧な使い方を教えるより、「考えるきっかけ」を与えることが、家庭での金融教育ではとても大切です。
おすすめの実践アイデア
おこづかい制を続けていく中で、少し工夫を加えると、学びの効果がさらに高まります。
たとえば「3つのビン」方式。もらったおこづかいを以下の3つに分けて管理する方法です。(ビンである必要はないです)
- 貯める(貯金)
- 使う(自由に使う)
- わける(誰かのためや寄付)
視覚的にもわかりやすく、お金の使い道を意識する習慣がつきます。また、簡単なおこづかい帳やアプリを使って、何に使ったかを記録するのもおすすめです。親が「見せてごらん」と言うより、子どもから「これに使ったよ!」と話してくれるようになると理想的です。
最後に:おこづかいは「お金の教育」への入り口
おこづかいは、単なる現金のやり取りではなく、「選ぶ」「我慢する」「振り返る」といった多くの力を育てるチャンスです。
金額の多さや使い道よりも、「親子でお金について話す時間があるかどうか」がなにより大切。子どもが失敗しても責めずに、「じゃあ次どうする?」と一緒に考えていける関係が、金融教育の土台になります。
7歳という年齢は、「自分で考えて行動する」最初のステージ。そのタイミングで始めるおこづかい制は、子どもにとって一生モノの“お金感覚”を育てる第一歩になるはずです。