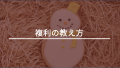教育資金の準備方法は様々ありますが、学資保険に加入するより積み立て投資するほうが合理的だと考えます。
どういったリスクに備えるか、考え方や状況は家庭によりますので絶対の正解はないですが、私の周りの人を見ていても、日本人は盲目的に学資保険に入りがちだと私は感じます。
手段の検討プロセスを行ったかどうかは非常に重要です。ちゃんと考えましょう、という話です。
教育資金準備の手段
子どもの教育資金を準備する方法のうち、日本では主に「銀行預金」と「学資保険」がメジャーとされています。
ソニー生命が毎年実施している調査結果によると、教育資金の準備方法について下記の結果でした。
面白いと思ったのは、「現在貯めている人」「既に貯め終わった人」の2つのアンケートを実施しているところです。これは参考になりますし、時代の変化も少し見えます。
現在教育資金を準備している層
- 銀行預金:56.4%
- 学資保険:43.7%
- 資産運用(投資等):19.0%
- 生命保険(学資保険以外):10.0%
- 財形貯蓄:9.4%
- 祖父母からの援助:5.6%
※複数回答式
出典:ソニー生命 子どもの教育資金に関する調査2024
既に大学まで進学した子を持つ親が準備した方法
- 銀行預金:69.0%
- 学資保険:39.9%
- 奨学金:17.3%
- 祖父母からの援助:10.9%
- 資産運用:10.5%
- 財形貯蓄:10.1%
※複数回答式
出典:ソニー生命 子どもの教育資金に関する調査2024
日本では「貯金」「学資保険」が一般的です。「貯金」のみ、という家庭は珍しいと思いますが、注目すべきは「学資保険」です。
40%超という多くの家庭が「学資保険」を選んでいます。
しかし、現代の経済環境、特に直近のインフレ環境では「本当に積立型の学資保険がベストな選択なのか?」を慎重に考える必要があります。
2023年以降、日本は30年ぶりの物価高を経験しています。私自身、1986年生まれなので人生初のインフレを経験している最中です。
最近はコンビニに売っているお菓子の値段を見ると、ほんとうにびっくりします。
円安やエネルギー価格の上昇を背景に、家計の負担は増加し、将来の学費も高騰する可能性が高いです。
この状況下で「受け取る金額が固定されている学資保険」が本当に教育資金を準備する手段として適正と言えるでしょうか。
本記事では「保険が教育資金の準備に向いていない理由」と、「より効率的な資産形成の方法」としての積立投資を説明します。
そもそも日本はなぜ「積立型保険」を選びがちなのか?
(1) 日本は生命保険大国
日本は世界で3番目に生命保険料の総支出が多い国(約2.9兆ドル)です。多くの家庭が、保険を「貯蓄手段」として利用しており、特に教育費の準備手段として学資保険が定番となっています。
しかし、欧米では教育資金の準備に保険を活用するのは一般的ではなく、株式投資や投資信託での資産形成が主流です。この違いは、日本の金融教育の不足や文化的な影響によるものです。
(2) 保険営業の影響を受けやすい
日本では、銀行や郵便局の窓口で保険商品が販売されるため、
- 「元本保証」
- 「確実に戻るし、増える」
- 「貯蓄もできる」
といった営業トークに安心感を抱き、深く考えずに契約してしまう人が多いです。しかし、これらの保険商品はリターンが低く、何より「インフレリスク」を考慮できていません。
元本割れよりも、インフレ考慮がないことのほうがリスクだと感じます。
リターンも低く、インフレ時代において圧倒的に不利な学資保険。それならば投資信託で資産運用するほうが良いと思います。
学資保険 vs. 積立投資:どちらが有利か?
具体的なメリット・デメリットを挙げてみます。
| 項目 | 学資保険(積立型保険) | 積立投資 |
|---|---|---|
| 期待リターン | 約1%以下 | 年平均4〜7% |
| 途中引き出し(流動性) | 不可(解約時に元本割れ) | 可能(タイミング調整可) |
| インフレ対応 | 弱い(資産価値が下がる) | 強い(資産が増える) |
| 柔軟性 | 低い(契約固定) | 高い(自由に増額・減額可) |
いくつか挙げてみましたが、私が考える大きな差は以下の2点です。
(1) 途中引き出し(流動性)の違い
学資保険に限らず、多くの保険がそうですが、途中解約すると元本割れが起こります。そのため、契約期間中は積み立てたお金が柔軟に使えません。
子どもの進路希望はどうなるか分かりませんので、流動性はかなり気になる点です。
一方、投資なら「必要なときに必要な分だけ」取り崩すことができます。もちろん投資の場合も元本割れの可能性はあります。
(2) インフレ対応の違い
学資保険は受取額が固定のため、インフレが進むと価値が目減りします。
例えば、学資保険で300万円受け取る予定でも、20年後の価値は240万円相当になる可能性があります。
投資資なら、インフレとともに成長し、将来の購買力を維持できます。
シミュレーション:学資保険 vs. 積立投資(S&P500など)
次に、どの程度の差が開くかを計算してみます。学資保険の平均支出をもとに、月に2万円とします。
(1) 学資保険の場合
- 月2万円を15年間積み立て(総額360万円)
- 返戻率112%とすると、最終的に400万円の受取。
(2) 積立投資(S&P500連動投資信託)の場合
- 月2万円を年利5%で15年間運用 → 約520万円(元本360万円+運用益160万円)
- 必要なときに柔軟に引き出し可能(教育費・塾・留学費など)。
あくまで単純なリターンです。インフレによる物価上昇で、更に差は開く可能性もあります。
リスクしか感じない学資保険
ここまで挙げてきた通りです。
恐らく学資保険に加入するときに、途中解約のリスクは重々承知だと思います。ですが、ここまで急激にインフレが進むことは予想しづらいと思いますし、予想はするものでもありません。
子どもの進路に加え、市場環境がどうなるかも全くわからない状況で、18年という長期の(途中解約で損をする)学資保険を契約することはリスクではないでしょうか。
他方、学資保険に加入される方にとってのメリットは何かというと恐らく保険の機能(死亡保障)だと思います。
この「保険」という機能が、複雑さを加えている要因だと思います。
保険は保険、投資は投資、で機能別に適した商品を選択するべきですが、むしろ一緒になっていることが魅力的だとアピールされることが多いでしょう。
だからこそしっかり比較・検討することが重要なのです。
実践:「積立投資」に移行する方法
学資保険から積立投資への移行について考えます。
(1) まずは保険を見直す
これが一番重要です。学資保険に限らず、現在の加入保険をきちんと整理してみましょう。
- 「本当に積立保険が必要か?」を考える。
- 必要なら掛け捨ての定期保険に変更し、コストを抑える。
死亡保障であれば掛け捨ての定期保険で十分です。
各社でシミュレーションページが大体存在するので、計算してみましょう。
積立型の保険に入っている場合、解約=損です。払済保険に変更できないか、確認しましょう。
(2) 余剰資金で資産運用に移行
保険の見直しで余った資金を投資信託に回しましょう。NISA口座があれば活用しましょう。
- S&P500や全世界株式のインデックスファンドを活用。
(3) 具体的な積立計画
| 積立額 | 15年後の予想金額(年5%運用) |
| 月1万円 | 約260万円 |
| 月2万円 | 約520万円 |
| 月3万円 | 約780万円 |
ちゃんと考えて手段を選びましょう
今回は教育資金ということで学資保険について書きましたが、積立型保険全般に同じことが言えます。
- 教育資金としていつまでにいくら必要かを検討する
- 定期的にメンテナンス(見直し)する
- 保険が必要なら掛け捨てを使う、保険と投資は分ける
- ちゃんと考える
保険という商品に対して全くの無駄だとは思っていません。私自身、医療保険と定期保険に加入しています。(いずれも掛け捨て)
ですが、やはり機能が違うものを1つの商品に詰め込んだらそれは無理が出るというものです。
保険に加入するのは我々です。
自分が購入する金融商品(保険も含む)のことは比較・検討して本当に必要か、他に手段はあるか、をちゃんと考えましょう。
貯蓄から投資へ、という時代の流れが来ていますが、(積立型)保険から投資へ、の方も同時にやっていくべきだと思います。